契約書の作成と聞くだけで、「難しそう」「自分には無理かも」と感じたことはありませんか?
私自身、業務委託契約や秘密保持契約などを用意するたびに、「どの条項が必要?」「この書き方で大丈夫?」と不安になり、いつもひな形を探しては微調整していました。
でも、最近はChatGPTが契約書作成の“アシスタント”として使えることを知り、活用するようになったんです。
正確な法律判断はできないとはいえ、構成の雛形を作ったり、条項を自然な日本語で整えてくれたりと、驚くほど実用的でした。
この記事では、ChatGPTを使って契約書を効率よく作成するためのプロンプト例や使い方の工夫を紹介します。
法務担当ではない方や、初めて契約書を扱う方にも、安心して活用できるヒントが詰まっています。
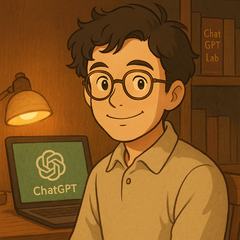
ChatGPTで契約書作成を“スマートに”進めるプロンプト設計術
契約書作成というと「一字一句ミスできない」というプレッシャーから、つい億劫になってしまう人も多いはず。
でも、ChatGPTはこの作業を“スマートに、手早く、しかも丁寧に”進めるための強力なパートナーになります。
ここでは、契約書の基本構成を自動生成させるプロンプトの工夫と、ChatGPTの“質問力”を活かした設計方法をご紹介します。
基本構成・条項指定・注意点まで、AIが契約書作成の補助役に!
業務委託契約書の基本的な雛形を作成してください。
成果物・報酬・納期など、典型的な条項も含めてください。
ChatGPTの出力例(一部抜粋):
第1条(目的)
本契約は、発注者が受注者に対して業務を委託し、その業務の成果物を納品させることを目的とする。
このように、主要な構成を自動で出力させることで、「何を書けばよいか分からない…」という悩みが一気に解消されます。
加えて、下記のような追加指示を加えることで、より実務に即した文面に近づけることが可能です。
契約解除の条件や、損害賠償責任についても明記してください。
すると、ChatGPTは関連する条項を追加し、「第10条(契約の解除)」や「第11条(損害賠償)」などを自動挿入してくれます。
法務初心者でも使いやすい!誤解を防ぐプロンプトの工夫とは?
法律用語を使いつつ、難しすぎない自然な文章で表現してください。
法務の経験が浅い場合でも、こうしたトーン指定を行えば、読み手に配慮した表現に仕上げてもらうことができます。
また、曖昧な表現を避けるためのプロンプトも非常に有効です。
「なるべく」「できる限り」など曖昧な言葉を使わず、具体的な表現にしてください。
このように、ChatGPTに「法律っぽさ」だけでなく、「読みやすさ」と「誤解のなさ」を同時に求めることで、実務でも扱いやすい文案が得られます。
ChatGPTで契約書を作成するメリットと注意点
ChatGPTで契約書を作ることには、多くのメリットがあります。
一方で、法的責任や実務面での限界も存在します。ここでは、活用するうえで知っておきたい「強み」と「注意点」の両方を整理します。
時間短縮・文案のヒント・構成整理ができる利点
ChatGPTは、構成のベースを一瞬で出力してくれるので、白紙から書き始めるストレスを大幅に軽減できます。
さらに「この条項、どう表現すればいい?」というときにも、言い回しのアイデアや例文を提示してくれるので、草案作成の効率が大きく上がります。
複数の契約書を並行して扱う場合も、ChatGPTが構造の統一や順序整理を助けてくれるため、ミスの予防にもつながります。
ただし「法的最終チェック」は専門家の確認が必須
当然ながら、ChatGPTは弁護士ではありません。
出力された文章が法的に正しいか・有効かは、AI自身が保証することはできません。
特に、損害賠償・契約解除・準拠法などの重要条項は、専門家のチェックが不可欠です。
実務で使用する前には、必ず弁護士などの確認を通すことを前提に使いましょう。
実務に使えるレベルか?の見極め基準を知る
ChatGPTの出力がそのまま実務に使えるかは、契約の種類・用途・リスクの大きさによって大きく異なります。
たとえば、業務委託の単発案件や、社内用の簡易な覚書などは、ChatGPTの草案をベースにして問題ないケースも多いでしょう。
一方で、金額が大きい・取引相手が慎重・裁判リスクがあるといった契約には、AIの草案をそのまま使うことは避けるべきです。
“たたき台”としてChatGPTを活用しつつ、リスクの重みに応じた使い分けを意識することが大切です。
契約書作成でよく使うプロンプト設計の基本
ChatGPTで契約書を作成する際、どのようなプロンプトを使うかによって、出力の質が大きく変わります。
ここでは、実務でよく使うプロンプトの3タイプを紹介し、目的別の使い方を整理します。
「業務委託契約書のひな形を作成してください」など汎用依頼
業務委託契約書のひな形を作成してください。
納期、報酬、成果物の定義などを含めてください。
ChatGPTの出力例(一部):
第3条(成果物の内容)
受託者は、甲が指定する仕様に基づき、成果物を納品するものとする。
第5条(報酬)
報酬額は金30万円(消費税別)とし、納品後30日以内に乙に支払うものとする。
「守秘義務条項を詳細に入れて」など条項単位の追加指示
この契約書に、守秘義務条項を追加してください。
秘密情報の範囲・保存期間・違反時の対応も盛り込んでください。
ChatGPTの出力例(一部):
第8条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の情報を第三者に開示してはならない。
2. 秘密情報の保持期間は、契約終了後2年間とする。
「法的に曖昧な表現は避けてください」といった表現の工夫
文章内の曖昧な表現をなくしてください。
「可能な限り」「できるだけ」などを具体的な記述に変更してください。
ChatGPTの出力例(一部・修正前後比較):
修正前:委託者は、可能な限り早急に成果物を確認し…
修正後:委託者は、成果物納品日から3営業日以内に内容を確認し…
【応用】業種や契約形態、条件を指定した“網羅的プロンプト”
以下の条件に基づいて、準委任契約書を作成してください。
・契約形態:準委任契約
・業種:Webシステムの保守運用
・作業内容:月20時間以内の軽微な修正対応
・契約期間:2025年6月1日〜2025年11月30日
・報酬:月額10万円(税別)
・秘密保持、契約解除、瑕疵対応、再委託禁止、準拠法・管轄条項も含めてください。
ChatGPTの出力例(一部):
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対してWebシステムの保守運用業務を準委任することに関し、必要な事項を定めるものである。第2条(業務内容)
乙は、甲が指定するWebシステムについて、軽微な修正・更新を月20時間以内で対応する。第3条(契約期間)
本契約の有効期間は、2025年6月1日から2025年11月30日までとする。第4条(報酬および支払方法)
甲は、乙に対し、報酬として月額10万円(消費税別)を支払う。第5条(秘密保持)
乙は、本契約に関連して知り得た甲の業務上の秘密を、契約期間中および契約終了後2年間、第三者に漏洩してはならない。第6条(瑕疵対応)
乙の業務遂行に起因する不具合が生じた場合、乙は甲の求めに応じて速やかに修正対応を行う。第7条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。第8条(再委託の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。第9条(準拠法および合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
業務内容や契約形態を具体的に指定することで、ChatGPTは実務に即した草案を驚くほど精密に出力します。
シチュエーション別:契約タイプごとのプロンプト例
契約書にはさまざまな種類があり、それぞれに押さえておくべきポイントがあります。
ここでは、代表的な3タイプの契約について、ChatGPTにどう依頼すれば実務に耐える草案が出力されるかをご紹介します。
業務委託契約:業務範囲と報酬の明示
業務委託契約書の作成をお願いします。
業務内容はECサイトのUI改善で、月30時間の作業時間制限を設けます。
報酬は月額15万円、納品物は簡易レポートです。
ChatGPTの出力例(一部):
第2条(業務内容)
乙は、甲が運営するECサイトにおけるUIの改善業務を行うものとし、月30時間を上限とする。
第4条(報酬)
報酬は月額15万円(税別)とし、翌月末までに支払うものとする。
秘密保持契約(NDA):第三者提供・保存期間の指定
秘密保持契約書を作成してください。
秘密情報の保存期間は契約終了後2年、第三者への提供は原則禁止。
例外事項と違反時の対応も含めてください。
ChatGPTの出力例(一部):
第3条(秘密情報の管理)
受領者は、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
秘密保持期間は契約終了後2年間とする。
売買契約:支払い条件と所有権移転の明記
売買契約書の草案を作成してください。
対象物はオフィス機器、支払いは納品後30日以内、所有権は代金完済後に移転します。
ChatGPTの出力例(一部):
第5条(所有権の移転)
本商品の所有権は、乙による代金の全額支払い完了時に甲から乙へ移転するものとする。
第6条(支払条件)
乙は、甲に対し、商品納品後30日以内に全額を支払うものとする。
このように、契約書の種類に応じて「押さえるべき条項」は異なります。
ChatGPTには、それらを明確に伝えることで、より精度の高い草案を得ることができます。
ChatGPTを法務ツールとして活かすポイント
ChatGPTは「契約書のすべてを任せる存在」ではありません。
しかし、草案作成や文案の調整、論点の洗い出しなど、“補助ツール”としては非常に優れたパートナーです。
ここでは、実務に落とし込む際に意識したい使い方のポイントを3つ紹介します。
出力結果を“たたき台”として使い、専門家レビューへ回す
ChatGPTの出力は、最初の草案として非常に有効です。
法務知識が十分でなくても、ひな形をもとに専門家と相談できる状態をすぐに作れるのが大きなメリットです。
「ゼロから考える」よりも、「たたき台を修正する」ほうが相談もしやすく、レビューの効率も高まります。
重要ワード・法律用語の説明もプロンプトで依頼可能
以下の契約書草案で使われている法律用語を、非専門家向けにやさしく説明してください。
このような依頼をすると、「瑕疵」「再委託禁止」「準拠法」などの用語について、簡潔かつ実用的な説明を加えてくれます。
社内説明資料や提案書などにも応用でき、社外への契約提示時の補足資料としても活用できます。
条項単位で編集→再生成を繰り返しブラッシュアップ
第5条(報酬)の表現をもう少し明確にしてください。
締め日と支払日を具体的に記述したいです。
条項ごとに指示を出しながら、ChatGPTに再生成を依頼することで、完成度の高い文案へ段階的に近づけていくことができます。
これはWordなどで自分で修正するよりも、筋の通った文体で整えてくれる点で特に便利です。
ChatGPTは「法務の代替」ではなく、「契約作成を支えるチームメンバーのひとり」として、上手に育てていきましょう。
まとめ:契約書作成を“もっと身近に”するAIの使い方
ChatGPTを活用すれば、専門知識がなくても契約書のたたき台を自分で作れるようになります。
「契約書は弁護士しか作れない」という思い込みを取り払い、日常業務に近い感覚で作成・見直し・調整ができるようになるのです。
本記事では、以下のようなポイントをご紹介しました:
- 契約書の構成・条項を自動で出力する基本的なプロンプト設計
- 業務委託・NDA・売買契約など、シチュエーション別の活用例
- 曖昧表現の排除や、読みやすい文面への書き換え指示
- 専門家チェックを前提とした“法務補助ツール”としての活かし方
もちろん、最終的な契約締結には法律の専門家の目が欠かせません。
ですが、ChatGPTという“賢いパートナー”を味方につけることで、法務リテラシーの底上げや時間とコストの大幅な節約が実現できます。
ぜひ、あなたの業務にも“AI契約書アシスタント”を取り入れて、契約業務のハードルをひとつ下げてみてください。



コメント