「このスライド、いったい何を伝えたいの?」
プレゼンや社内共有の資料を作っていて、そんなふうに指摘された経験はありませんか?
私自身、伝えたいことが頭にあるのに、構成がバラバラで相手にうまく届かない…。そんな悩みを何度も抱えてきました。
そんな中で活躍してくれたのが、ChatGPTです。
構成案を考えてもらったり、要点を整理してもらったり、さらには発表原稿のたたき台まで用意してくれる。今では、私の“スライド作成パートナー”になっています。
この記事では、ChatGPTを使ってスライドの構成・内容・表現を整えるための具体的なプロンプトと活用術を、実例を交えて紹介します。
「伝わる資料を、もっと効率的に作りたい」そんなあなたに役立つ内容をお届けします。
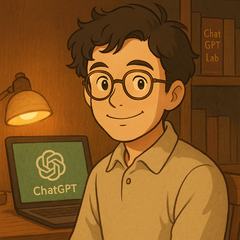
「この資料、何が言いたいの?」と言わせないスライド構成の作り方
…
要点整理→構成化→補足文の生成まで、AIで効率UP!
…
スライド作成にありがちな悩みとAIの出番
話が散らかる・構成に自信がない・時間が足りない…
スライド作成では「言いたいことが整理できない」「構成が思い浮かばない」「納期が迫って焦る」といった悩みがつきものです。
情報の粒度や優先度をどう扱うかでつまずくと、思考が止まり、資料づくりが進まなくなってしまいます。
そんな時こそ、ChatGPTが強い味方になります。
以下に、よくある課題とそれを解決するプロンプト例を紹介します。
このスライドで伝えるべきポイントを3つに絞ってください。
前提:新規プロジェクトの提案/マネージャー向け
ChatGPTの出力例(一部):
・提案の背景と目的
・解決策の概要
・期待される効果と投資対効果
このように、ChatGPTは要素を整理し、伝えるべき“芯”を明確にしてくれます。
自分の思考を“整える”補助ツールとしてのChatGPT活用
ChatGPTは、単に“文章を代わりに書くツール”ではありません。
頭の中にある情報を並べ直したり、順序を考えたり、言語化のサポートをしてくれる「思考整理アシスタント」として機能します。
次の3つの項目について、話の順番や構成案を考えてください。
・サービスの強み ・導入実績 ・今後の展望
ChatGPTの出力例(一部):
1. 導入実績で信頼感を示す
2. サービスの強みを訴求
3. 今後の展望で期待感を演出
このように、ChatGPTの提案から逆に自分の考えが整理され、「この順番の方が伝わるな」と納得感を得ることができます。
スライドの目的別(説明・提案・報告)に応じた使い方
スライドの用途に応じて、構成や表現は大きく変わります。
ChatGPTには、目的を明示して依頼することで、その場にふさわしい提案が得られます。
このプレゼンは「新製品の社内説明会」で使います。
説明型のスライド構成を5枚程度で提案してください。
ChatGPTの出力例(一部):
1. 製品開発の背景と課題感
2. 新製品の概要と機能紹介
3. 競合との差別化ポイント
4. 活用事例とユースケース
5. 社内展開に向けた今後の予定
提案や報告といった目的を示すことで、ChatGPTの出力精度は一段と高まります。
「誰に、何を、どう伝えるか」を明確にすることで、資料作成が“企画力のある仕事”に変わっていきます。
ChatGPTに頼めるスライド作成支援とは?
テーマに合った構成案の提案
まず最も基本的な活用法が、「このテーマで、どんな構成が適切か?」を相談することです。
ChatGPTは、PREP法(結論→理由→具体例→再主張)やSDS法(概要→詳細→まとめ)などの論理展開パターンを用いた構成案も提示してくれます。
PREP法に沿って、次のテーマでスライド構成を提案してください。
テーマ:テレワーク導入の社内推進プレゼン
ChatGPTの出力例(一部):
1. 【結論】テレワーク導入は社内の生産性を高めるために必要
2. 【理由】従業員満足度の向上とオフィスコスト削減が可能になる
3. 【具体例】他社での成功事例と社内アンケート結果の紹介
4. 【再主張】だからこそ、今すぐテレワーク導入を推進すべき
構成の型を使うことで、資料の論理性が高まり、聞き手の納得感も生まれやすくなります。
各スライドに載せるキーポイントの抽出
構成が決まったら、次は“各スライドで何を伝えるか”を具体化していきます。
ChatGPTは、説明すべき要点を絞り込み、重要度順に並べることも可能です。
スライド3「具体例」に載せるべきキーポイントを3つ挙げてください。
ChatGPTの出力例(一部):
・A社:テレワーク導入で離職率15%改善
・B社:年間800万円のオフィス費削減
・社内アンケートで85%が導入に賛成
内容を膨らませるというより、「伝えるべき核」を明確にすることに重点を置くと効果的です。
補足説明文・発表原稿のたたき台作成
最後に、実際にプレゼンを行うことを想定し、補足説明や発表原稿のたたき台を依頼するのもおすすめです。
ChatGPTはスライドの意図をくみ取って、100〜150字程度の説明文やトークスクリプトを作ってくれます。
スライド3「具体例」に対応する発表用の補足説明文を作成してください(120字程度)。
ChatGPTの出力例(一部):
「他社事例や社内調査を踏まえると、テレワーク導入による効果は明確です。コスト削減と働きやすさ向上の両面から導入を後押しできます。」
こうした“あと一歩”を補ってくれるのが、ChatGPTの頼もしさ。
考えを補完しながら、最終的には自分の言葉で仕上げていくスタイルが理想です。
効果的なプロンプト設計と活用フロー
ステップ1:構成の“前提条件”を共有せよ
ChatGPTに「スライド構成を考えて」とだけ伝えても、精度の高い案は出てきません。
まずは、以下の3点を明示することで、構成提案が格段に良くなります。
- 目的:説明か提案か、理解促進か説得か
- 対象:誰に向けたプレゼンか
- テーマ:話す内容・狙いたい印象
例えば、以下のような違いが生まれます。
【条件なしでの依頼】
このテーマでスライド構成を考えてください。
テーマ:会議削減の提案
ChatGPTの出力例(一部):
1. 会議の課題点
2. 調査結果の紹介
3. 会議削減のメリット
4. 提案内容
5. 導入時の注意点
【条件ありでの依頼】
スライド構成を5枚で提案してください。
目的:上司への業務改善提案 対象:課長職 テーマ:会議削減の提案
ChatGPTの出力例(一部):
1. 会議の現状と課題
2. 時間的コストの影響
3. 改善案の提案
4. 効果と試算
5. 実行計画とサポート依頼
ステップ2:出力の粒度をコントロールする
ChatGPTの出力は、プロンプトの“粒度(どのくらい細かく指定するか)”によって大きく変わります。
たとえば「3つのポイントを箇条書きで」「100字以内で説明して」など、形式を具体的に伝えると意図に沿った結果が得られます。
スライド3「改善案の提案」に載せる要点を、3つに絞って提示してください。
ChatGPTの出力例:
・週次会議を隔週開催に変更
・定型報告はSlackでの事前共有に切り替え
・議題の事前送付と目的の明確化
ステップ3:“調整の対話”で完成度を高める
最初の出力が完璧である必要はありません。
むしろ、「この点を強調して」「もっとフォーマルに」などの指示を重ねることで、ブラッシュアップされていきます。
この3つの要点に補足説明文を付けてください。文章トーンはビジネスフォーマルで。
ChatGPTの出力例(一部):
「定例会議の開催頻度を見直すことで、準備・実施にかかる時間を全体で30%削減可能です。特に報告型会議については、代替手段の導入が効果的です。」
ステップ4:一貫した指示で“ほぼ完成形”に到達できる
構成を固め、各ページに「要点」「補足説明」「タイトル」を順に依頼していくことで、次のような“スライドの原型”が整います。
スライド1:会議の現状と課題
【タイトル】「会議はなぜ多すぎるのか?」
【要点】
・1週間あたりの会議時間は平均8.6時間
・非生産的な会議が全体の3割を占める
・参加者の集中力・満足度が低下している
【補足説明】
「社内調査によると、会議の長時間化・頻度過多が業務集中を阻害しているとの声が多く上がっています。」スライド2:時間的コストの影響
【タイトル】「1時間の会議は本当に1時間か?」
【要点】
・参加人数×時間で実質工数が拡大
・資料準備や移動時間の負担も大きい
・会議あたりコスト換算が明確でない
【補足説明】
「5人で1時間の会議を行えば、5時間の工数消費。見えない“時間コスト”を可視化することで改善の意識が高まります。」スライド3:改善案の提案
【タイトル】「ムダ会議削減の3ステップ」
【要点】
・週次会議を隔週開催に変更
・報告型会議はSlack共有に代替
・目的と議題を事前明示し、短時間化
【補足説明】
「3つの取り組みを通じて、年間約500時間の削減が期待できます。小さな改革が全体の効率化につながります。」スライド4:効果と試算
【タイトル】「“500時間削減”がもたらす影響」
【要点】
・1時間×500回=500時間の削減
・残業抑制や集中時間創出への効果
・従業員満足度と離職率の改善も期待
【補足説明】
「年間500時間の削減は、人件費ベースで約150万円相当。業務の質向上やストレス軽減にも寄与します。」スライド5:実行計画とサポート依頼
【タイトル】「スモールスタートで始めよう」
【要点】
・まずは1部署でパイロット導入
・1か月後に振り返りと効果測定を実施
・運用定着に向けた部門間連携を強化
【補足説明】
「まずはスモールスタートで始めることで、失敗リスクを抑えながら改善サイクルを回せます。管理職の協力が鍵となります。」
このように、同じ形式のプロンプトをスライドごとに適用すれば、トーンと論理の整った“プレゼン資料のたたき台”を短時間で整えることができます。
ChatGPTとの対話は、“伝える力”の設計を助けてくれる、思考補助ツールそのものです。
チェックを経て完成度を高めたスライド例(最終版)
前セクションで作成したたたき台を、チェックポイントの視点で再検討し、以下のように改善しました。
スライド1:会議の現状と課題
【タイトル】「“なぜ多すぎる?”会議の実態を可視化」
【要点】
・会議時間が1週間で平均8.6時間
・3割が非生産的という調査結果
・集中力・満足度の低下が深刻
【補足説明】
「現状の会議運用には多くの無駄が潜んでおり、特に“目的不明・準備不足”な会議が非効率化を招いています。」スライド2:時間的コストの影響
【タイトル】「“1時間の会議”=“5時間分の工数”」
【要点】
・参加人数×時間=実工数として換算すべき
・事前準備・後処理の負荷も無視できない
・1回の会議が蓄積的に効率を下げる
【補足説明】
「1時間×5人=5時間、これが毎週だと年250時間。目に見えにくい“会議の損失コスト”にもっと目を向ける必要があります。」スライド3:改善案の提案
【タイトル】「“ムダ削減3原則”で会議体改革へ」
【要点】
・定型会議はSlack共有へ移行
・週次会議を隔週化し、集中開催
・目的と議題を事前提示し短時間化を徹底
【補足説明】
「簡単な変更でも、時間の使い方が大きく変わります。定型を非同期へ、判断会議は目的明示で短縮。これが削減の鍵です。」スライド4:効果と試算
【タイトル】「500時間削減=150万円超の効果」
【要点】
・1部署あたり年間500時間の短縮効果
・人件費換算で約150万円の削減に相当
・業務改善と働きやすさの両立も実現
【補足説明】
「可視化された成果があることで、他部署展開にも説得力が増します。“時間の見直し”が経営資源の見直しにもつながるのです。」スライド5:実行計画とサポート依頼
【タイトル】「いますぐ始める“スモールステップ”改革」
【要点】
・1部署で1ヶ月のパイロット導入
・定量評価とフィードバックを実施
・成果次第で他部署展開を段階的に進行
【補足説明】
「この取り組みは大規模改革ではなく“小さく始めて確実に広げる”戦略です。まず一歩を踏み出すために、ご協力をお願いします。」
このように、構成・内容・トーン・論理の流れをChatGPTと対話しながら磨き上げていくことで、「伝える力のあるスライド」へと自然に進化させることができます。
伝わるスライドに仕上げるためのチェックポイント
1スライド1メッセージの原則とChatGPTでの検証方法
スライド作成における基本ルールのひとつが「1スライド1メッセージ」。
ひとつのスライドで複数のことを伝えようとすると、結局どれも伝わらないという事態になりがちです。
ChatGPTは、作成したスライドの内容を見せて「伝えたいメッセージが1つに絞れているか?」を問い直すチェックにも使えます。
このスライドの内容は、1メッセージに絞られていますか?
スライド内容:
「会議が多い現状と、削減に向けた施策案をまとめたもの」
ChatGPTの出力例(一部):
「2つの異なる論点(現状分析と施策提示)が混在しており、1スライド1メッセージの原則に照らすと分けて扱う方が効果的です。」
論理の流れを整える:ストーリー構成をAIで再点検
プレゼンの理解度や説得力を大きく左右するのが「全体のストーリー設計」。
PREP法、SDS法、FAB法などを使った場合でも、ChatGPTに全スライドを渡して流れの一貫性を確認できます。
以下のスライド構成は論理的な流れになっていますか?違和感があれば指摘してください。
1. 会議の課題
2. 削減施策案
3. 成果事例
4. コスト試算
5. 社内への呼びかけ
ChatGPTの出力例(一部):
「“成果事例”が“施策案”の後ろに来ると、読者が“先に成果が出ている根拠”を欲しがる可能性があります。順序を入れ替えると説得力が増します。」
表現のトーン・視覚要素のアドバイスも活用しよう
伝わるスライドは、構成と論理だけでなく、表現のトーンや視覚的な工夫にも左右されます。
ChatGPTに「もう少しカジュアルに」「データの視覚化に向いた構成に」などと頼めば、表現の方向性まで提案してくれます。
この内容を、若手社員向けにもう少しカジュアルな表現に変えてください。
「テレワーク導入で離職率が改善。コスト削減にもつながります。」
ChatGPTの出力例:
「テレワークを始めてから、働きやすくなったと感じる社員が増えました。実はコストも下がって、会社にもプラスです!」
このデータをスライドで視覚化するなら、どんな図表が向いていますか?
・オフィス利用率:前年80% → 現在45%
・会議時間:月40時間 → 月25時間
ChatGPTの出力例:
・オフィス利用率は“時系列折れ線グラフ”
・会議時間は“ビフォーアフターの棒グラフ”が適しています
表現の工夫にもChatGPTを活用すれば、“伝わりやすさ”までデザインできるようになります。
チェックを経て完成度を高めたスライド例(最終版)
前セクションで作成したたたき台を、チェックポイントの視点でChatGPTと再検討すると、以下のように改善されました。
スライド1:会議の現状と課題
【タイトル】「“なぜ多すぎる?”会議の実態を可視化」
【要点】
・会議時間が1週間で平均8.6時間
・3割が非生産的という調査結果
・集中力・満足度の低下が深刻
【補足説明】
「現状の会議運用には多くの無駄が潜んでおり、特に“目的不明・準備不足”な会議が非効率化を招いています。」スライド2:時間的コストの影響
【タイトル】「“1時間の会議”=“5時間分の工数”」
【要点】
・参加人数×時間=実工数として換算すべき
・事前準備・後処理の負荷も無視できない
・1回の会議が蓄積的に効率を下げる
【補足説明】
「1時間×5人=5時間、これが毎週だと年250時間。目に見えにくい“会議の損失コスト”にもっと目を向ける必要があります。」スライド3:改善案の提案
【タイトル】「“ムダ削減3原則”で会議体改革へ」
【要点】
・定型会議はSlack共有へ移行
・週次会議を隔週化し、集中開催
・目的と議題を事前提示し短時間化を徹底
【補足説明】
「簡単な変更でも、時間の使い方が大きく変わります。定型を非同期へ、判断会議は目的明示で短縮。これが削減の鍵です。」スライド4:効果と試算
【タイトル】「500時間削減=150万円超の効果」
【要点】
・1部署あたり年間500時間の短縮効果
・人件費換算で約150万円の削減に相当
・業務改善と働きやすさの両立も実現
【補足説明】
「可視化された成果があることで、他部署展開にも説得力が増します。“時間の見直し”が経営資源の見直しにもつながるのです。」スライド5:実行計画とサポート依頼
【タイトル】「いますぐ始める“スモールステップ”改革」
【要点】
・1部署で1ヶ月のパイロット導入
・定量評価とフィードバックを実施
・成果次第で他部署展開を段階的に進行
【補足説明】
「この取り組みは大規模改革ではなく“小さく始めて確実に広げる”戦略です。まず一歩を踏み出すために、ご協力をお願いします。」
このように、構成・内容・トーン・論理の流れをChatGPTと対話しながら磨き上げていくことで、「伝える力のあるスライド」へと自然に進化させることができます。
まとめ: ChatGPTで“伝える資料作成”の新しい形へ
- 「この資料、何が言いたいの?」と言われないために、構成設計から始めることが重要。
- ChatGPTを使えば、スライドの構成・要点・補足文・表現まで一貫して設計できる。
- プロンプトの工夫で出力精度を高め、完成度の高い“たたき台”を短時間で生成できる。
- 完成後も、チェックポイント(1スライド1メッセージ、論理の流れ、トーンの調整)を通じて洗練できる。
- ChatGPTとの対話は、「思考の整理」と「伝え方の設計」を支援してくれるパートナー的存在。
プレゼンや報告資料を作る時間がない、構成が苦手、自信が持てない――そんな悩みは誰にでもあります。
でも、ChatGPTを活用することで、「伝える資料をラクに、早く、わかりやすく」仕上げることができる時代になりました。
大事なのは、丸投げすることではなく、一緒に考えてもらうこと。
構成を相談し、内容を磨き、表現を調整する。
そんな“共同作業”ができる相手として、ChatGPTを活用してみてください。
あなたの次の資料作成が、もっと楽しく、もっと伝わるものになりますように。


コメント